「絵本は子どもの心の成長を促します」
と聞くと、へそ曲がりなぼくは、
・絵本以外の事柄だって心は成長するだろうに。片手落ちじゃないか?
とか
・作者は心の成長を意識して描いてるのかよ。そんな本気持ち悪くて読みたくねぇや。
とか。
言いようのないキモチワルさを感じることがよくある。
「この本を読んでも子どもの心は成長しません!」
「むしろ退化しちゃいます!」
という絵本があっても、炎上目的のイヤラシさを感じてしまうだろうから厄介なものだ。
というわけで、「心の成長」というヤツを頭の中でなにか別の言葉に変換するなり、市民権を与えてやる必要にかられたぼくは、少し深堀りしてみることにした。
「心の成長」とは具体的に何を指すのだろうか?
そして、そもそも心は「成長する」のか、それとも「変化する」のか?
この問いを掘り下げることで、本屋さんで、web検索で、ぼくの心がかき乱されることが少なくなるのかもしれない。
目次
1. 「成長」という言葉の持つ意味
成長とは、一般的には「大きくなること」「より優れた状態に進むこと」を指す。たとえば、身長が伸びることや、運動能力が向上することは明確に「成長」と言える。
しかし、心はどうだろうか?
たとえば、以前は泣いてばかりいた子が、次第に感情をコントロールできるようになることを「成長」と捉えることがある。また、他者の気持ちを理解できるようになったり、新しい価値観を受け入れたりすることも「成長」と呼ばれることが多い。
しかし、これらは本当に「成長」なのだろうか?
ちょっと子どもが大きくなって、できることが増えて、という時期に甘えん坊さんに一時的に逆戻りしてしまう「退行現象」というものがあるらしい。この尺度でいくと退行現象期間中、人間は退化していることになってはしまわないか。
2. 「変化」としての心の動き
心のありようは、固定されたものではない。
子どもは環境や経験によって、日々変わり続けている。昨日まで怖がっていたものに今日は興味を持つこともあれば、好きだったものが突然つまらなくなることもある。
この変化の過程を「成長」と捉えることもできるが、実際には「適応」や「変化」と言ったほうがしっくりくる場合も多い。
たとえば、ある子が以前は虫が苦手だったが、昆虫図鑑を読み、実際に触れてみることで興味を持つようになったとする。この場合、「成長」というより「変化」だと考えるほうが自然ではないだろうか。
また、共感力が高まることを「成長」とするならば、それは「他者との関わりの中で生じた変化」と言い換えられる。決して一方向的に高まるわけではなく、環境によっては後退することもある。そう考えると、心は「成長するもの」ではなく、「変化し続けるもの」と言えるかもしれない。
3. 「成長」という言葉がもたらすプレッシャー
「成長」という言葉を使うと、どうしても「今よりも良い状態になることが望ましい」というニュアンスが含まれる。
しかし、すべての変化が前向きなものとは限らない。
たとえば、以前は素直に気持ちを表現していた子が、周囲の目を気にして感情を隠すようになった場合、それは「成長」なのだろうか? あるいは、新しい環境に適応するための「変化」なのか?
また、「成長することが良いことだ」という考え方は、子ども自身にプレッシャーを与えることにもつながる。「もっと頑張らなきゃ」「できるようにならなきゃ」と思うあまり、本来の自分を見失うこともあり得る。
そう考えると、子どもを「成長させる」ことに固執するのではなく、「どのように変化しているのか」を見守る視点が大切なのかもしれない。
4. 変化を受け入れるために
では、「成長」ではなく「変化」という視点で子どもを見守るためには、どのような心構えが必要だろうか?
・固定観念を持たない
「この子はこういう性格だ」と決めつけず、その時々の変化を受け入れる。
・良い変化も、そうでない変化も受け入れる
「もっと優しくなってほしい」「もっと積極的になってほしい」といった願いを押しつけるのではなく、そのままの状態を見守る。
・変化のプロセスを大切にする
何かを「できるようになった」ことだけでなく、「なぜそうなったのか」「どんなきっかけで変化したのか」に目を向ける。
5. 「成長」よりも「変化」を楽しもう
心は成長するのではなく、変化するものだと考えると、子どものありのままを受け入れやすくなる。
今日の子どもと、明日の子どもは違う。
それは「成長した」からではなく、「変化した」から。
その変化を、親子で一緒に楽しんでいくことこそが、何よりも大切なのではないだろうか。
ということで溜飲を下げることにする。

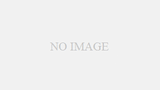
コメント