毎日仕事でクタクタになって帰ってきて、子どもがすでに寝ていた――なんてこと、きっとたくさんの親にとって「あるある」だと思う。コロナがあけて以前の出社ありきの労働環境に戻りつつあお父さんやお母さんにとって、子どもとの平日の時間は貴重で、ほんの一瞬しかない。
友人の家庭もまさにそうだ。お父さんは朝早く家を出て、帰宅は夜10時過ぎ。子どもは幼児期まっただなかで、日中はママと過ごし、パパの顔を見るのは休日だけというサイクル。休日はできるだけ子どもと遊ぼうと、公園に連れて行ったり、お出かけに行ったりはしている。けれど、読み聞かせのような「静かな親子の時間」はなかなか持てていない。
でも実は、読み聞かせって「時間があるときにだけやるもの」じゃないと思っている。むしろ、ちょっとした工夫やマインドの転換で、忙しい毎日の中でも無理なく取り入れることができる。今日はそんな「読み聞かせを日常に組み込むコツ」をお伝えしたい。
目次
1. 「疲れてるから無理」なのは当然。まずはそれを受け入れよう。
まず何よりも大切なのは、「疲れているのにできない」と自分(or 配偶者)を責めないこと。
読み聞かせは、たしかに子どもにとっても親にとっても素晴らしい時間になる。でもそれは「義務」ではないし、「やらなきゃいけない」ことでもない。できない日は、素直に「ああ今日はできなかった」で終わっていい。むしろそんな日常の中で、ぽつんとでも「読んでみようかな」という気持ちが出たときに動けたら、それだけですごい。
「毎日やる」が目的ではなく、「やれるときに楽しめる」が大切だ。
2. 寝落ちを受け入れたら、すべてが楽になった
僕自身、読み聞かせを習慣にできたのは、「子どもと一緒に寝る」と決めてからだった。
世間には「子どもが寝てからが大人の時間」と言われるけれど、それって実はすごく無理がある。子どもを寝かしつけて、そこからやっと自由時間だなんて、疲れていたら起きていられるわけがない。
だから、発想をひっくり返してみた。「子どもと一緒に寝てしまおう」と。そうすれば、布団に一緒に入る流れで絵本を読む時間が自然とできる。しかも、子どもも親も満たされて、そのままスーッと眠れてしまう。
これが、我が家の読み聞かせの最適解だった。大人の時間は、翌朝早く起きられたらラッキーくらいでいい。
3. 「読む」より「開く」ことを目標にする
読み聞かせというと、きちんと座って、抑揚をつけて、全ページ読みきる……というイメージがあるかもしれない。でも、それがしんどいなら、もっとラフでいいんじゃなかろうか。
例えば、「今日は2ページだけ読もう」と決めて開くだけでもOK。いや、「表紙だけ眺める」「好きなページだけ読む」でもいい。
重要なのは、絵本というメディアに触れること。その瞬間の「親子で一緒に本を開く」という体験が大切なのだ。だから、「読む」という行為のハードルを思い切って下げていい。
(別で書いた「あと100回作戦」と対立する考えだが、元気なときに「あと100回」をすればよいのである)
4. 子どもは「読む内容」より「一緒にいる空気」で満たされる
意外と知られていないが、子どもが喜ぶのは「どんな本を読んだか」よりも、「誰と、どんなふうに過ごしたか」だ。
極端な話、疲れていて棒読みになっても構わない。途中で寝落ちしてしまってもいい。むしろ、その「がんばらなさ」が子どもにとっては安心につながることもある。
たった数分でも、「パパが隣で絵本を開いてくれた」という経験が、子どもの心にはしっかり残る。忙しい日々の中で、その一瞬が宝物になる。
5. 短くてテンポのいい本を味方にする
長編絵本じゃなくてもいい。短くてテンポがよく、リズムのある絵本を選ぶと、疲れていても読めるし、子どもも楽しめる。
僕のおすすめは、擬音語や繰り返しのある本。「ぽんぽんぽん!」「ぴょーん!」など、読むだけで気分が上がるし、子どもも真似したり笑ったりしてくれる。
ときには、お気に入りの一冊を何度も読むのもいい。読むたびにリアクションが違うから、親もだんだん面白くなってくる。
6. 週1でも月2でも、子どもは覚えている
「毎日読み聞かせている家庭」に引け目を感じることはない。どんな頻度でも、子どもは覚えているし、喜ぶ。
むしろ、「たまに読んでくれるパパがいる」ということは、それだけでも子どもにとっては特別な出来事。月に一度のスペシャルイベントでも構わない。
読み聞かせは「頻度」よりも「密度」。目の前の時間をどう楽しむかが大事だ。
7. 小道具に頼るのもアリ
どうしても疲れているときは、音声付き絵本や読み聞かせ動画に頼ってもいい。親が声を出さなくても、画面を一緒に見て反応するだけで、コミュニケーションになる。
ただし、動画を見せっぱなしにはせず、「一緒に見る」ことが大事。一緒に笑ったり、驚いたりすることで、親子のつながりが育まれる。
8. 子どもが寝た後の「自分時間」に、未来の読み聞かせを仕込む
読み聞かせは、読むだけがすべてではない。絵本の選書や、置き場所を考えることも「仕込み」として大事な準備になる。
仕事の合間にネットで絵本を調べたり(その際に当ブログが役に立てばそれは嬉しいことだ)、帰りに本屋に立ち寄って1冊買って帰るだけでもいい。「こんなの見つけたよ」と言って手渡すと、それだけで親の存在感がぐっと増す。
物理的に一緒にいられない時間でも、「次に一緒に読む絵本」があると思えば、それは心の中でずっとつながっていられる仕掛けになる。
まとめ:読み聞かせは「心の切り替えスイッチ」になる
外で働く親にとって、家庭と仕事の両立は本当にたいへんだ。とくに幼い子どもを育てる時期は、ただでさえ余裕がなく、自分の時間なんて夢のまた夢だ。
そんな中でも、ほんの一冊、ほんの一瞬の読み聞かせは、心の切り替えスイッチになりうる。
「子どもと目を合わせる時間」「ただ一緒に過ごす時間」がそこにあるだけで、仕事モードから、家族モードへと自然に戻ってこられる。
毎日は無理でも、週1でも、月2でも、気負わず続ける。それがいつか、子どもにとっても自分にとっても、かけがえのない記憶になる。
仕事で疲れ果てた夜こそ、勇気を出して、子どものとなりに潜り込もう。そして、1冊、開いてみよう。

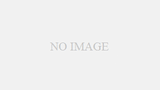
コメント