子どもに絵本の楽しさを伝えるためには、読み聞かせを習慣化することが大切だ。そのためには、自然と絵本に触れられる環境を整え、親も一緒に読書を楽しむ姿勢を見せることが鍵だと考えている。
本記事では、いつでも絵本にアクセスできる環境づくりと読み聞かせをする習慣づくりの我が家の工夫について紹介してみることにする。
目次
1. 絵本の供給体制を整える
子どもが絵本を楽しむためには、手元に読みたい本があることが大前提だ。
子どもが定期的に新しい絵本に出会える仕組みを作ることで、興味を引き続けることができると信じている。
● サブスクを利用する
最近では、毎月定額で絵本が届くサブスクが充実している。プロが選んだ絵本が自宅に届くため、親が選ぶ手間が省けるだけでなく、普段自分では選ばないような本と出会えるメリットもある。
子どもにしてみれば、毎月自分宛ての小包が届くわけで、プレゼントを開封する的な楽しさも提供できているかもしれない。
● 図書館を活用する
定期的に図書館に通う日を決めると、親子で絵本選びを楽しむ習慣ができる。図書館には多種多様な絵本がそろっており、気軽にたくさんの本に触れることができるのが魅力だ。
我が家は二週間に一度の金曜日、近所の中央図書館に行って上限の20冊まで借りてきている。
● 「本屋さんで1冊選んでいいよ」ルール
本屋さんに行ったときに「今日は好きな絵本を1冊選んでいいよ〜」とすることも検討にいれたい。
子ども自身が選んだ本ならば、愛着が深まり大切に読むようになるだろうなぁ、的な発想なのだが、いかんせんこの頃の本屋さんは商業商業した絵本を平積みにしてあり、「うっそ音がなるだけで1冊2000円!?」みたいなオドロキがあったりなかったり。。
2. 読み聞かせの習慣をつくる工夫
供給体制は整った。後は実際に読み聞かせをするのみである。
とはいえこれは習慣づけなければ意味がない。子どもに習慣づける、というよりもむしろ親の方の習慣づけが必要で、親が無理なく続けられる工夫を取り入れることで、自然と絵本の時間が生活の一部になるのではないかと思っている。
(自分含めて世の親御さんは、なにかにつけて「疲れた」「忙しい」「あとで」を口にしがちなわけで)
● 枕元に本棚を置く
寝る前に読む本を枕元の本棚から選ぶようにすると、絵本を手に取るのが当たり前の習慣になる。子ども自身が自分で本を選ぶことで、自主的に読む意欲も高まる。
我が家では国語辞典とマーカーもセットで置いている。わからない言葉が出てきたら、もしくは親がしっかりと説明できない言葉が出てきたら辞書を引くことにしている。これについてはまたいずれ書きたい。
● 親も読書をする
子どもは親の行動をよく見ている。親がスマホばかり見ていると、子どももスマホに興味を持ってしまう。そこで、親もスマホを置いて本や雑誌を読むようにすると、子どもも「本を読むことが普通」と感じるようになる。
● 日中も絵本の話をする
絵本の世界を日常会話に取り入れることで、物語の内容がより身近に感じられるようになる。例えば、「この前読んだ絵本に出てきた〇〇みたいだね!」と話題にするだけで、子どもは物語を思い出して楽しむことができる。
● 「絵本もっといで!」の声かけ
ベッドに行く前に「絵本もっといで!」と声をかけると、子どもが自分で絵本を選ぶ習慣がつく。遊び感覚で本を手に取る流れができるため、スムーズに読み聞かせタイムに移行できる。
まとめ
読み聞かせを習慣にするには、まず絵本を身近に置き、定期的に新しい本に触れられる仕組みを作ること。そして、親自身が読書を楽しむ姿を見せることで、子どもも自然と本を好きになっていくのではなかろうか。と仮説をたてて活動している。
「絵本を読もう!」と意識しすぎるのではなく、「いつでも読める環境」を整えることが、長く続けるコツかもしれない。今後も日々の生活の中に、無理なく絵本を取り入れていきたい。

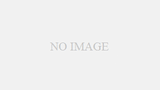
コメント